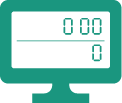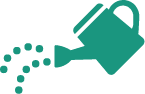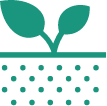一歩、踏み込んだ遮熱対策の取り組み(施設編)
各地で稲刈りが始まりました。流通価格が話題にのぼりますが、高温・少雨・渇水・水害などの気象環境からの収量や品質への影響が懸念されています。さて、今回は施設での遮熱対策の取り組み事例を紹介します。

施設栽培では、フィルムや防虫ネットで被覆されていることもあり、ハウス内の気温は外気よりも高くなるのが一般的です。まずは、いかに外気まで近づけていくかということが求められます。ハウス内の気温を外気まで近づける外気導入を検討や設置される生産者が今年は増えています。

あるイチゴの生産者は、毎年、一定の設備投資を続けられ、年々、環境が厳しくなる中でも、育苗の環境を整え、苗品質の維持をされています。近隣や他産地での育苗が苦戦される中、結果として、高品質で、丈夫な苗を育てられている形になっています。
| これまでの取り組み | ・底面給水にて育苗(タイマー潅水) ・遮熱剤(レディヒート) ・遮熱ネット外部開閉(手動・涼感ホワイト、2023年) ・簡易ミスト(自ら施工、2024年) |
| 今年の新たな取り組み | ・外気導入(アウトサイダー) |
| その他 | ・定植時の活着促進・枯死対策として、保水材(ゲインウォーター)を検討 ・本圃は日射比例潅水(潅水NAVI)を導入中 ・育苗ハウスは周辺の生産者より、間口広く、軒高も高い |




高温への対策は、遮熱ネットをひとつとってもに、黒系のネットで強い日差しを遮ることからはじまり、より熱を反射する白系の遮熱ネットが主流になりました。また、これまで遮熱ネットを用いていなかった北海道や東北、高冷地などの地域でも導入が進みましたが、一般地では遮熱ネット頼りの対策では限界があります。
また、害虫への対策を強化するため、より目合の細かいネットが展張されるようになりましたが、近年は、害虫の被害や防除の作業負担を理解した上で、高温対策のために粗い目のネットを採用される方もでてきています。
昨年は9月以降も暑い日が続き、中生の水稲や露地の秋冬野菜に大きな影響を与えました。今年は例年より梅雨明けが早く、高温が2ヵ月近く続いている状況になっています。品種や作型の変更だけでは対応できず、これまでどおりの対策では限界に到達しています。
今後のさらなる気温上昇や機関の持続を見据えて、昨今、注目されているバイオスティミュラント(BS)資材も含めた複数の対策の組み合わせ、これまで行っていなかった取り組みの導入していくことが求められています。